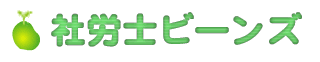
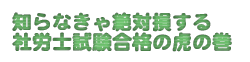
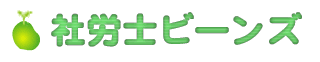 |
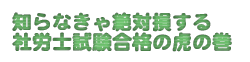 |
| 白書の一般非常識!の部 |
| 今回は、令和6年版厚生労働白書から「労働者を取り巻くストレスの現状」についての出題です。昨今、社会課題ともなっている精神疾患について、本試験対策として理解を深めておきましょう。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。
厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、2022(令和4)年は【82.2%】であった。 一方、【50歳代】は「仕事の量」が最も高く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が高くなっている。なお、【60歳以上】はストレスと感じる事柄を1つも選択しなかった人が最も多かったが、ストレスがある人のストレスの内容では、「仕事の質」が最も高く、次いで「【対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)】」となっている。 また、就業形態別にみると、正社員は「仕事の量」、「仕事の失敗、責任の発生等」の順に高くなっているが、契約社員や【派遣労働者】では「雇用の安定性」の割合が高い傾向があり、特に【派遣労働者】では突出して最も高い。 このように、ストレスを感じている労働者は非常に多いが、その要因や背景は、年代や就業形態などにより多様であることが分かる。 仕事の量は労働者の主要なストレスのひとつといえるが、仕事量の多さは労働時間の長さとして現れる場合も少なくない。 総務省「労働力調査」の月末1週間の就業時間別の雇用者割合の推移をみると、1週間の就業時間が【60時間以上】である雇用者の割合は、【2003(平成15)年】をピークとして、働き方改革の進展等により、緩やかな【減少傾向】を示しているが、2022(令和4)年は【5.1%】と前年より0.1%ポイント【増加】した。 また、月末1週間の就業時間が【60時間以上】である雇用者数は298万人と前年より約8万人【増加】した。1週間当たりの実労働時間別のうつ傾向・不安についてみると、労働時間が【長く】なるにつれて、うつ病・不安障害(重度のものを含む)の疑いがある人の割合が【増加】する傾向がみられる。 また、労働時間が【長く】なるにつれて、翌朝に前日の疲労を持ち越す頻度が【増加】する傾向がみられ、その頻度が【増加】すると、うつ病・不安障害(重度のものを含む)の疑いがある人の割合が【増加】する傾向もみられる。こうしたことから、労働時間がこころの不調につながる背景には、【長時間労働による疲労の蓄積】があるとみられる。
ご理解は進みましたでしょうか。 |
![]()